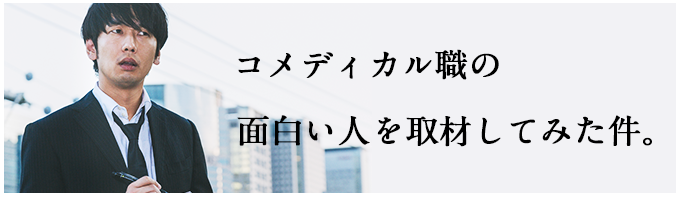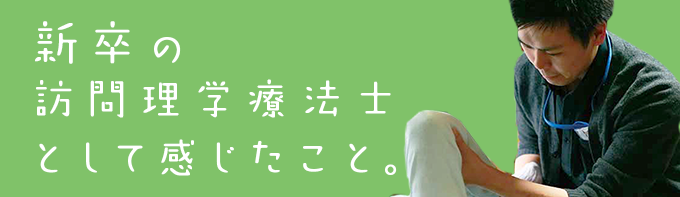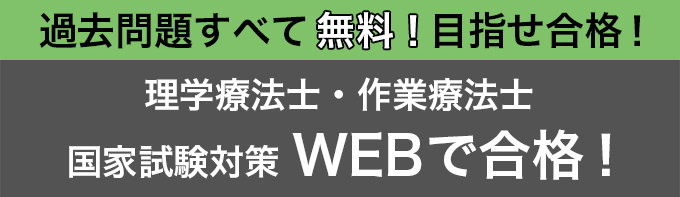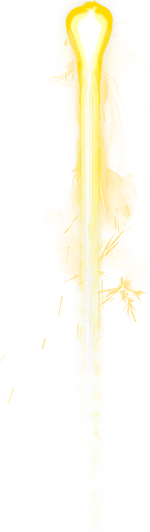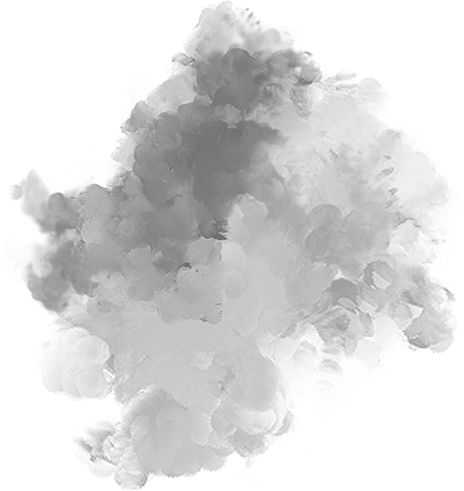1月16日の日本経済新聞朝刊に以下の見出しで記事が掲載されていました。
「混合介護」を「国家戦略特区」で展開する構想を東京都と豊島区が調整を進めているという記事。
日本経済新聞以外にも数多のメディアで取り上げられ、注目度の高さがうかがえます。
朝日新聞:混合介護特区を豊島区検討 保険と対象外サービス併用
「混合介護 東京・豊島区で -保険外を同時提供-」(日本経済新聞 2017年1月16日朝刊)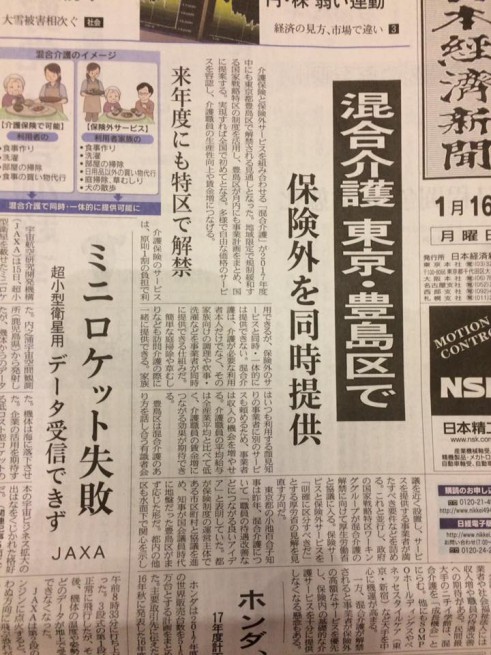
現状でも違法ではない
現状の介護保険法は混合介護を禁じているわけではなく、厚生労働省は保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することを認めている。しかし、両サービスを「明確に区分する」など一定の条件を求め、両サービスを「同時・一体的」に提供することはできない。
このように決して現状でも実施することができます。
しかしながら、明確に区分する必要性があり、その煩雑さから普及していない背景もあります。
マンパワーも少ない中、混合介護ならぬ「混同介護」になってしまうと現場レベルから声も上がってきているようです。
そうした状況を見ると、今回の特区は結構画期的だと考えます。
以下に理由を書いていきます。
1.介護保険と一体的になるため多種多様な業務が可能
混合介護は、介護が必要な利用者本人だけでなく、その家族向けにも調理や炊事・洗濯などを事業者が同時に提供できる仕組みだ。
この仕組みをわかりやすい例えでいうと、今までの介護保険内サービスでは洗濯や掃除をしてもらう際、その家族の分の食事を作ってもらうことはできませんでした。
しかし、混合介護になるとその間に家族分の食事を支度したり、草むしりをしたり、部屋の片づけをしたりすることができるようになります。
今後、労働人口が減り、”支える側”が少なくなっていく中では生産性の面からも画期的だと言えます。
2.介護士の給与UPの期待
事業者の収入の機会が増える。介護職員の平均給与は全産業平均より低く、事業者の経営や職員の待遇の改善が課題だった。
周知の通り、介護職員の平均給与は低く分類され、多くの事業収入割合を介護保険報酬に頼らざるをえないために社会保障費が逼迫している現状ではそうそう上がる見込みはないといわれています。
そんな中で処遇改善加算等の施策が始まったものの、事業主としてしてやはり安定的・継続的に収益を生む「成長」の柱を求めます。
他方、保険内に頼らず自費だけの介護で事業が成り立つ(代表的なところはグレースケアでしょうか)と言われているように、市場としては”画期的な介護サービス”を求めている側面もあります。
同時・一体的に介護が提供できるようになることは、これまで規制されていた時間当たりにこなせる業務(本人だけでなく家族へのサービスetc)増え、必然的に事業収入が増えます。
先ほども言いましたが、生産性が上がるだけでなく事業収益も増えるため、結果的に給与に反映されると考えるのが自然でしょう。
デメリットは?
・保険外の高額サービスが優先される
・自立を妨げる(介護を過度に入ると)
・経済格差によって受けられるサービスに差が出る
など、挙げればキリがないですが現状を打破するためには前向きに考え、議論をしていくことが求められます。
(執筆:細川寛将)
\ SNSでシェアしよう! /