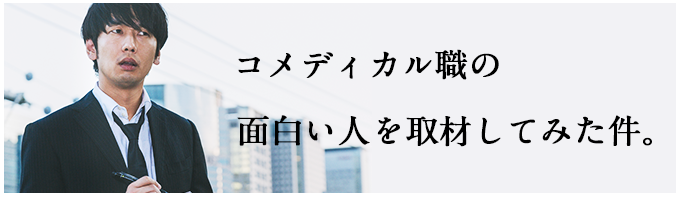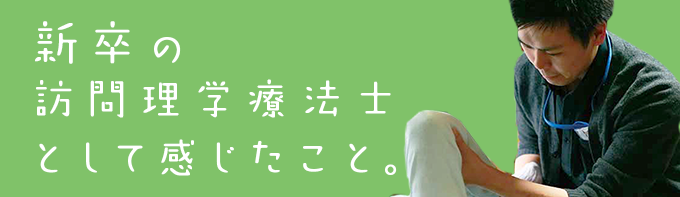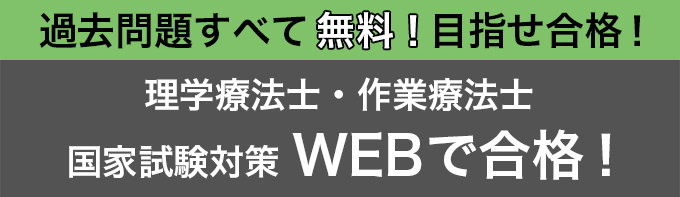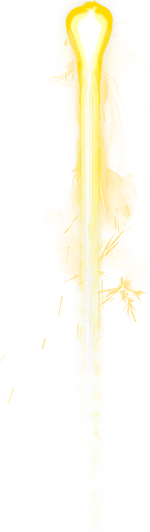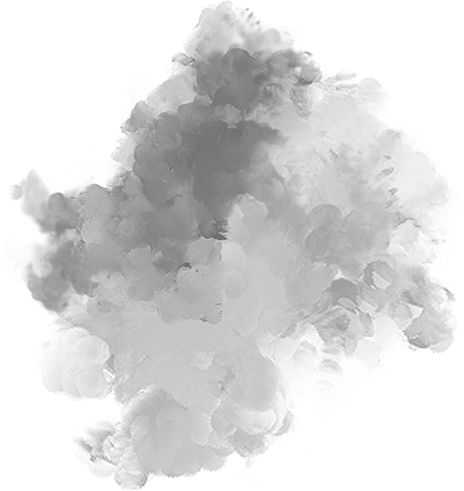家事支援の市場規模
経済産業省が2016年に発表した「家事支援サービスについて」というデータによると、将来的に家事支援サービスの市場規模は6000億円になると試算されてます。
なんと現在の健康食品市場と同程度です。
ぺット関連市場や国内ゲーム市場よりも大きいのです。
しかし、家事支援サービスの利用は現在たったの2%。
今後、市場が拡大するために必要な条件のとは何でしょうか?

家事支援サービスへの「補助」
「現在、家事支援サービスを利用していない理由」のランキングを抜粋してみました。
一位は「価格が高い」
二位は「必要性を感じない」
三位は「他人に家の中に入られることに抵抗がある」参考:平成26年3月14日発表 経済産業省 家事支援サービスについて
やはり、一番のネックは「価格」ですね。
経産省も結論として「価格面では、利用者負担軽減のための方策を検討する必要がある」としていました。
そのような中、愛知県が「家事支援サービスの利用者負担を2割にする!」と宣言し、協力企業を募集しました。
共働き世帯や働く女性を対象として、家事支援サービスを1回2時間 5回利用できます。そして、利用料金4万円のうち8割を愛知県が補助してくれます。
「まずは家事支援サービスを使ってもらう!」という強い意志と方向性を感じますね。
実際に、国はホームヘルパーによる家事支援を排除し、その仕事を家事代行業者に担わせる方針を示しています。

ある会社の実例:ビザスク
ビザスクというコンサル会社では、社員に対して「月2回までの家事代行サービス」を全額補助する制度があります。
シングルマザーで社長の端羽英子氏は「自分が家事代行を体験して時間を有意義に過ごすことの大切さを、身をもって感じたから」この制度を始めたとのことです。
端羽氏はシングルマザーになった後、ビザスクという会社を立ち上げました。
今は中学3年生の娘をひとりで育てています。
社長業と生活を両立させる為には、時間を有効活用する必要があります。
そこで注目したのが「家事代行サービス」でした。
これまでも「家事代行サービス」と「生活の満足度」に関する記事を書いてきましたが、端羽氏の場合はズバリ「時間をお金で買うことで満足度を得る」というモデルのようなケースです。
端羽氏によると、代行サービスを使わない人は「金銭的な問題より家事を人に頼むなんて申し訳ない、という罪悪感のほうが大きい」とのことです。
そこで、「使わないともったいない」という気持ちにさせ、まずはサービスを使ってもらうために全額負担制度を始めました。
今では社員の半分以上がこの制度を利用しているそうです。

家事支援・家事代行が「幸せ」をもたらす
上記したような家事代行などの時間節約型サービスを使うと、「人生の満足度が高まり幸福度が増す」といわれています。
ただ、これまでは海外の代行サービス業者を対象とした報告がほとんどでした。
そこで、「日本国内における代行サービス」でも同じような結果が得られたのでお伝えします。
どこの国でも「代行サービスの利用」と「生活に対する満足度」は関係しているようです。
詳細は以下から。
「働く」「福利厚生」「家事代行」に関する意識調査
参考:http://news.nicovideo.jp/watch/nw2942181 マイナビニュース
この調査は、政府が推進する「働き方改革」を受け、福利厚生や家事代行に対する個人の認知・利用実態を明らかにするために行われました。
調査によると、家事代行サービスを利用したことのある人のうち60%が「生活に大変満足または満足」と回答しました。
一方、利用したことのない人で「生活に大変満足または満足」と回答した人は34%でした。
その差は1.76倍。
ちなみに、生活の満足度と就業の継続希望にも強い相関がありました。

おわりに
今後、共働き世代が増加することで家事代行サービスも盛り上がっていきます。生活の満足度向上の為の利用はもちろん、介護離職を回避する為にサービスを利用するシーンも増えていきそうです。
\ SNSでシェアしよう! /