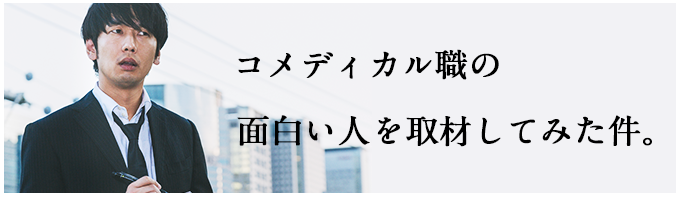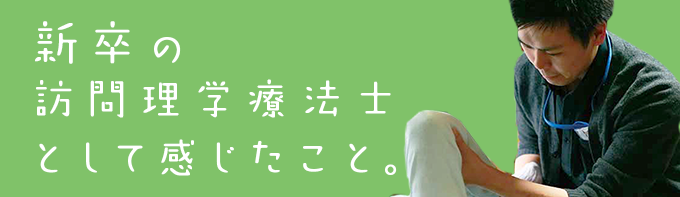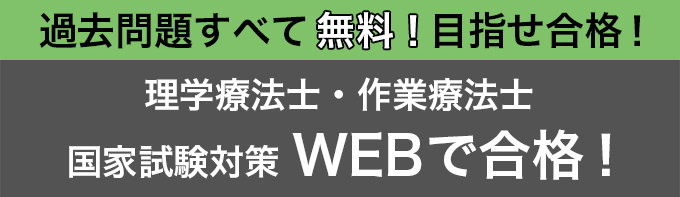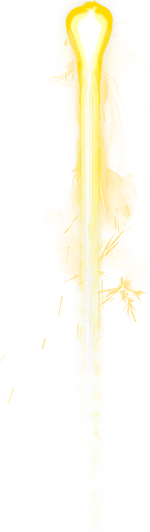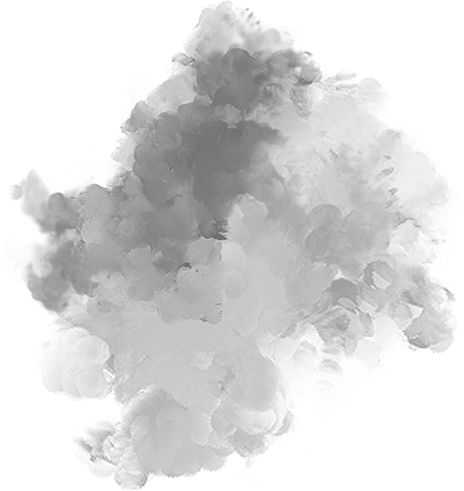皆さんは「農福連携」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。今、全国において、障がい者が農業の担い手となる「農福連携」が広がっています。
農林水産省と厚生労働省が中心となり、高齢化や後継者不足に悩む日本の農業に障がい者の就労機会を作ることで、新たな農業の担い手を作ることや障がい者の自立を手助けするのも狙いです。生産だけでなく、加工、販売まで手掛ける「6次産業化」に対して、障がい者の力を幅広く活用する組織が増えています。
米、野菜、果樹、牧場、養豚など、様々なジャンルで働く障がい者急増しています。農業の課題と福祉の課題、互いに連携し合うことでそれぞれの課題が解決されるの「農福連携」です。

【農業における課題】
1・農業労働者が半減
農業就業人口
H7年 414 万人 → H27 年 209 万人
2・高齢化の進展
農業者の平均年齢 66.3 歳
3・耕作放棄地の増加
H7~27 年で 18 万ha増加
【福祉における課題】
1.低い就業率
障がい者数 約788万人(18歳以上65歳未満の在宅者約324万人)
企業就労 約45万人(H27年6月)
福祉就労 約24万人(H26年10月)
2.低い工賃(福祉就労における)
H25年度 平均工賃 14,437 円 (月収)
農業と福祉が協力し合うことで、それぞれが単独では解決することができなかったことが解決できるようになることで、互いに「winwin」な関係となります。

さて、農業分野にて障がい者就労を本格化させる場合、いくつかのパターンがあると私は考えます。
- 福祉事業者が農業に進出し自ら農園を運営する
- 農業事業者が障がい者就労に進出し雇用する
- 福祉事業者と農業事業者がタイアップして運営する
の大きく3つに分けられるのではないでしょうか。それぞれの場面によっての課題や特徴が存在します。福祉と農業の知見を持つ人材の必要性、農地制度についての知識、農業と福祉の制度面での連携、作業適正や意欲など作業の質の確保が重要性であると研究からも言われています。
様々な課題はあるものの、障がい者だからこそ農業分野で活躍できる可能性があると私は強く感じます。
農業では自然との関わりが必ず存在します。種をまき、水をやり、芽が出て、草むしりをしながら世話をし、苦労をかけながら成長してく様を体験することで自分自身も成長します。時には自然の厳しさから失敗をすることもあります。暑い日も寒い日もあります。それでも、自然の中で行う農作業から得られる目に見えない力は心身の健康に好影響を与えるとされており、特に知的や精神障がい者へのリハビリ的な効果があります。
 農作業の様子1
農作業の様子1
【農業効果について】※H25年度 日本セルプセンター調査
障がい者就労支援事業所を対象としたアンケート
- 身体の状況がよくなった・改善した 45%
- 精神の状況がよくなった・改善した 57.3%
 農作業の様子2
農作業の様子2
また、農業は様々な作業から成り立っており、障がい者の特性に応じた作業を提供することが可能です。障がい者の特性を発揮する体制を構築しながら、事業として行う限り、また農家の担い手として行う限り、経営の安定・拡大を図っていけるかが大きな重要点かと感じます。

いずれにせよ、農業と障がい者をマッチングする場合、障がい者が農業にとって必要であること、そして、障がい者が作る作物(商品)であるからこそ、より付加価値ある作物(商品)であることを実践していくことが必要であると感じます。
農業だけに言えることではないですね。障がい者の方々を 1 人の戦力として捉え、社会の中で心から必要であると認められれば自然とその地域は活性化していくことでしょう。
このような地域社会を創ることは容易なことではありません。福祉だけでなく、農家だけでもなく、地域全体を創り上げていく新たな地域創りだと考えます。本当に健康に必要な作物を作っていくことが、これからの日本の農業です。
そこには障がい者の存在が必要です…。
\ SNSでシェアしよう! /