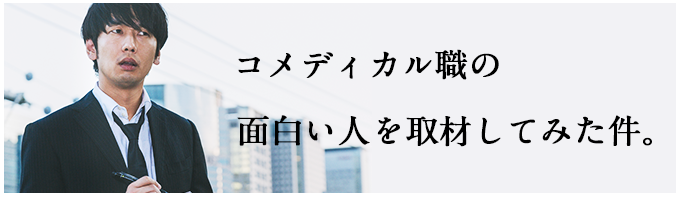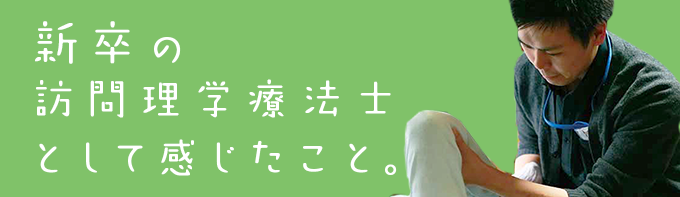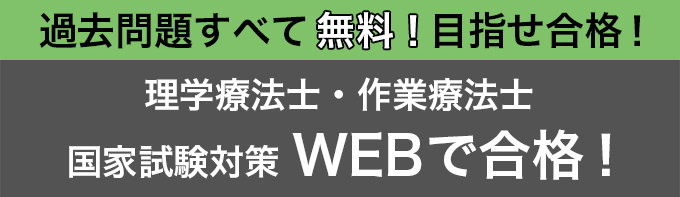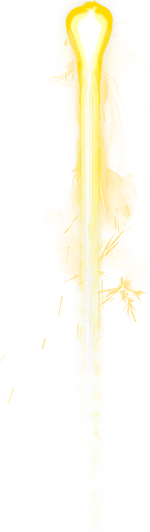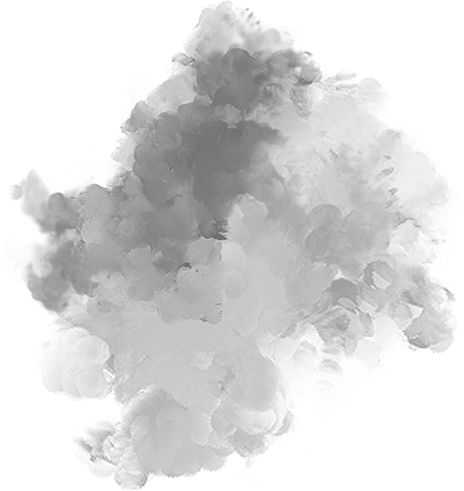地域ケア会議や介護予防では、介護保険制度の理念を基に進めていく事が重要になりますが、これらの考え方は地域住民の方も十分に理解できているでしょうか?

今回は市が主体となり市民へ介護保険制度の啓発活動を行った事例をご紹介します。
介護保険の「誤った」捉え方
介護保険は「自立支援」「悪化防止」「自らが状態の維持改善に努める」を理念として、その人の状態に合わせて適切なサービスを受けることができる制度ですが、
介護保険のサービスを「利用者が好きなように選んで使えるもの」「困りごとを解決するために使うもの」と認識されている場合も少なくありません。
この誤解は、平成12年の介護保険制度開始にあたり、介護保険法に書かれた理念である「利用者本位」「利用者の自己選択・自己決定」の言葉が先行してしまい、
その本当の意味を正しく理解してもらう取り組みが不十分のまま、サービスの利用が始まってしまったことが考えられています。
介護保険の正しい理解が不十分のままでは、適切なサービスが提供できなくなったり、介護保険サービスへの依存を生んでしまい、自立支援に繋げることが難しくなることが予想されます。

重要なのは「理念の共有」
この問題を解決するために、度々事例として挙げているW市では市職員が直接市民へ介護保険制度の理念を説明して回り、理解を促しました。
初めは理解が得られないこともありましたが、そうした利用者は地域包括支援センター職員と協力し個別に自宅へ訪問して根気良く説明することで、合意形成を図りました。
また、市民だけではなくケアマネージャーや介護保険サービスを提供する事業者に対しても繰り返し理解を促しました。
W市ではこうした官民一体となった啓発活動を今でも繰り返しながら、市全体で介護保険制度の共有を図っています。
このように保険者・介護サービス事業者・市民の3者で介護保険制度の理念を共有することが自立支援に資する取り組みが効果的に行う事ができたり、漫然としたサービス利用を防ぐことができます。

おわりに
介護保険サービスを卒業する場合にも抵抗なく総合事業等へ移行できることにも繋がってくるため、こうした啓発活動を行政や多職種で行うことも、街づくりへの取り組みにおいては重要な要素の一つになるのではないでしょうか。
記事提供

\ SNSでシェアしよう! /